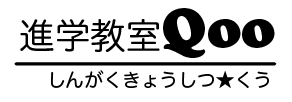Qooの塾長– Author –
東大・同大学院卒 農学修士。脳・身体・生物の進化とか生物系のこともろもろに興味あり。「考えるってこういうことか」と気づき、シンプルな思考を目指しています。
-

定期テストは“試合”であり“記録会”
昨日から定期テスト対策が始まりました。回を重ねるごとに、子どもたちの姿は少しずつ変化していきます。こちらからの発破を受けて動き出す子、自分の課題を自覚して自ら進化していく子、入試を意識して追い立てられるように机に向かう子──本当にさまざま... -

下ごしらえ、下ごしらえ。小学生英語の基礎づくり
勉強は料理と同じで、“下ごしらえ”がとても大切です。いきなり完成品を作るのではなく、まずは土台を丁寧に整えることが欠かせません。 ただいま小学生英語では「名詞の扱い方」に取り組んでいます。英語では名詞を使うときに「a」「the」の冠詞をつけるか... -

子どもが勉強に前向きになれない本当の理由
保護者の方から「うちの子は勉強に前向きでない」「勉強の必要性を感じていない」というご相談をいただくことがあります。結論から言えば、それは子どもの資質ではなく、これまでの育て方の影響が大きいと考えています。 本来、人が生きていく・サバイバル... -

作業=数学?子どもが陥りやすい勘違い
数学を教えていてよく感じるのは、「訳もわからず作業を繰り返すことが数学の勉強だ」と思っている子が少なくないということです。では、なぜこうなってしまうのでしょうか。 一つは、教えられ方の問題です。「この手順で解けばよい」と方法だけを覚える形... -

英語は“幹”を育てることから
中学1年生の英語指導を続けてきて、最近ぐっと基礎力がついてきたのを感じます。普段から、日本語をしっかり分析し、一つひとつ丁寧に考えながら英文に直す練習を積み重ねてきました。それを繰り返すことで、少しずつ成果が形になってきています。 特に大... -

親の本気が、子どもの本気を引き出す瞬間
先日、中学のある学年のクラスでこんな出来事がありました。小テストがいまいちで、このままでは成果につながらないと感じたため、「いっそ数学の授業はやめましょうか?」と保護者の方にLINEでお伝えしました。 すると、その日の夜、ご家庭で家族会議... -

ハングリー精神は大事
勉強でもスポーツでも、伸びる子って結局「もっとやりたい」「負けたくない」って気持ちが強いんです。ハングリー精神ですね。 で、このハングリー精神って、実は親が全部与えちゃうと育ちにくい。「困ったらすぐ助けてくれる」「欲しいものはすぐ手に入る... -

学力があることの強さ
「成績が下がってきたから塾に行こう!」「そこから一気に逆転してV字回復!」 …なんて話、ちょっと現実的には難しいものです。 なぜなら、学習の取りこぼしがある状態で新しい内容を吸収するのはとても大変だからです。学校のカリキュラムは「ちゃんと前... -

コツコツの積み重ね」
英語なんて、その最たるものですね。 毎日ひとつずつ教えて、毎回の小テストで確認して、少しずつ覚えていく。 その積み重ねが、ある日ふっと、目に見える形で大きな変化につながります。 だからこそ、日々の小さな努力を大切に。変化を楽しみにしながら、... -

外堀から埋める ― 英単語テスト
昨日の中1英単語テスト、結果がイマイチな子がちらほら…。時間もあったので、ちょっと手を打ってみました。 よくあるのは、「自分流」で勉強しているケース。一方で、しっかり結果を出している子は、こちらが伝えたやり方を素直に実践しているんです。つま...